

社内コミュニケーションとコミュニティを
自然発生させるWellness Aile
株式会社梓設計
一級建築士 岩瀬功樹 氏

経済産業省と日本健康会議が認定する「健康経営優良法人(大規模法人部門)」を取得している株式会社梓設計。社員一人一人が生き生きと活躍し、「豊かな人生」につながるような職場環境を作っている、健康経営のリーディングカンパニーだ。
健康に関する取り組みは継続が難しく、多くの企業が難航しているなか、梓設計はなぜ健康経営がうまくいっているのか。同社のこれまでの取り組みと「Wellness Aile」を導入することで生じた変化などについて、一級建築士で、AI・IoTなどデジタル活用のリーダーでもある岩瀬功樹氏に話を伺った。

建物の設計に、ウェルビーイングの要素は必要不可欠
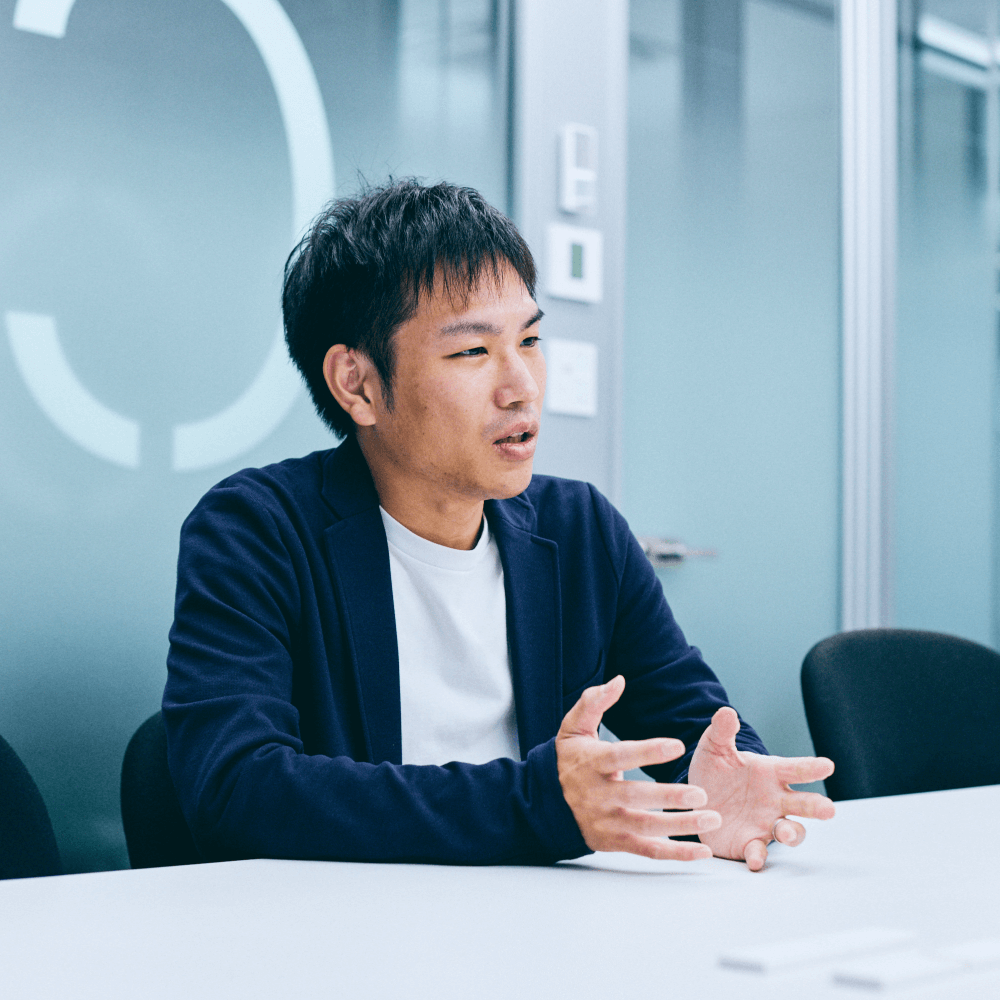
――まずは梓設計のミッションや事業を教えてください。
創業76年の梓設計は、「質実優美」を経営理念に「強靭かつ良質で、堅実に社会を支え、環境や人々への優しさを持ち、美しい由来を感じる形」を追求した建築物を設計している会社です。
作っているのは、空港やスポーツ施設、医療施設、教育施設、文化施設、商業施設、物流施設、都市開発など、多岐にわたる“社会から必要とされる施設や場所”。
温もりを感じられる設計にこだわっているのが特徴です。
――梓設計は、世の中で健康経営が注目され始めるずっと以前から、ウェルビーイングに取り組まれています。それは公共の施設や社会に高く貢献している建物を作っていることに関係しているのでしょうか。
そうですね。多くの人が集まる建物の設計にはウェルネスやウェルビーイングの要素が必要不可欠です。その建物を作ることで社会課題の解決につながり、さらに使う人たちが幸せや、働きやすさを実感できないと意味がありません。
普段の仕事で、常に人の健康や働きやすさを考えていることもあり、昔から健康や幸せに寄与するような取り組みが社内で自然発生していました。それが加速したのが、働き方改革が始まった頃です。会社の大きな変革期になり、健康や幸せ、生産性向上、働きやすさの度合いが高まった実感があります。
なかでも象徴的なのが、2019年に完成した新オフィスです。
「成長するオフィス」をコンセプトに、“働く人も建物も空間も成長することで、ウェルビーイングを常態化させること”を目指しています。

――「成長するオフィス」とは、具体的にどのようなオフィスなのでしょうか。
たとえば、コロナ前はプロジェクトの資料や収納物がある場所に、人が集まって仕事をしていました。しかしコロナ禍で社内のペーパーレス化が進み、資料の場所に人が集まる必要がなくなったため、プロジェクトごとに決めた場所にフラッグを立てて、そこに人が集まる運用に変えました。
すると、オフィスで働く人の位置情報から「どのプロジェクトにどのくらいの人が誘導されているか」、「コミュニケーションを多く取っていたプロジェクトは良い結果が出ているか」などを分析できるようになったのです。
プロジェクトの状況と結果が可視化されたことで、生産性やクオリティの向上、コミュニケーションの取りやすさにつながりました。これは1つの例ですが、こういった取り組みで働き方を変化していけることが、「成長する」ということだと考えています。
ボトムアップで複数の運動コミュニティが自然発生
――働き方改革をきっかけに始まった変革期で、取り組んだことを教えてください。
新オフィスは敷地からエントランスまで距離があること、広いワンフロアであることから、出社するだけである程度の運動につながるという利点がありました。それに加えて、大きな変革の起点となったのはApple Watchの全社導入でした。
特にコロナ禍においては、Apple Watchを活用したフィットネスイベントなどを企画すると大好評で、そこからいろいろなミュニティが社員の中で自然発生し始めました。たとえば週末にマラソンをするコミュニティや山登りをするコミュニティなどです。
――運動コミュニティが自然発生するのはすごいです。
もちろん、中には運動が嫌いな人もいると思います。でもトップダウンで何かを押し付けられているわけではないし、参加すれば会社から参加賞としてAmazonギフト券などがもらえるので、社員には“強制されている意識”がないのです。
完全なボトムアップでみんなが自由に動き始めたことを、会社がうまく吸い上げて福利厚生として社員に還元し、社員は健康になってパフォーマンスを発揮する。本来、健康経営で狙うべきことが自然にできていると感じています。

Apple Watchを全社導入。ウェルネスプログラムを浸透

――Apple Watchを全社導入されたというお話がありましたが、どんなきっかけがあったのでしょうか。
新オフィスに移転後、オフィス環境や働く人の動き、生産性などを可視化するために、位置情報や環境データなどを収集・分析するためのデバイスやIoT機器を導入しました。その一つが、約20名限定でトライアル導入したApple Watchです。
さまざまなデバイスでの実証実験の結果、仕事に直接関係ないデバイスは、用意してもなかなか装着してくれない、もしくは装着し忘れるなどにより、継続しにくいことがわかりました。
一方でApple Watchは、仕事だけでなくプライベートでも活用でき、ファッションとしても取り入れやすい。20名限定での実証実験をおこない、この仮説を上層部に提案した結果「それなら全社導入しよう」という意思決定をしてもらえました。
ただ、最初はApple Watchを装着してもらえても、データ収集と分析ができるアプリがなかったため、自分たちでアプリを開発する必要がありました。
それでも、なんとか自作のアプリや海外アプリを活用して、みんなで楽しめるウェルネスのプログラムを実施し、徐々にApple Watchの活用を社内に浸透させました。
そういった経緯があったため、「Wellness Aile」を紹介されたときは「これだ!」と思いましたね。導入すれば簡単にデータ収集と分析ができるので自分たちでアプリを開発する必要がありません。
それだけでなくゲーミフィケーション要素やインセンティブ要素もあるため、みんなが楽しんで続けられるという点も魅力的でした。まさに自らが楽しんで体を動かすためのサービスだと感じ、すぐにでも導入してみたいと思いました。
ただ、いきなり全社導入はハードルが高いので、まずは労働組合の約130名にテスト導入しました。
コミュニケーションとコミュニティを生む「Wellness Aile」
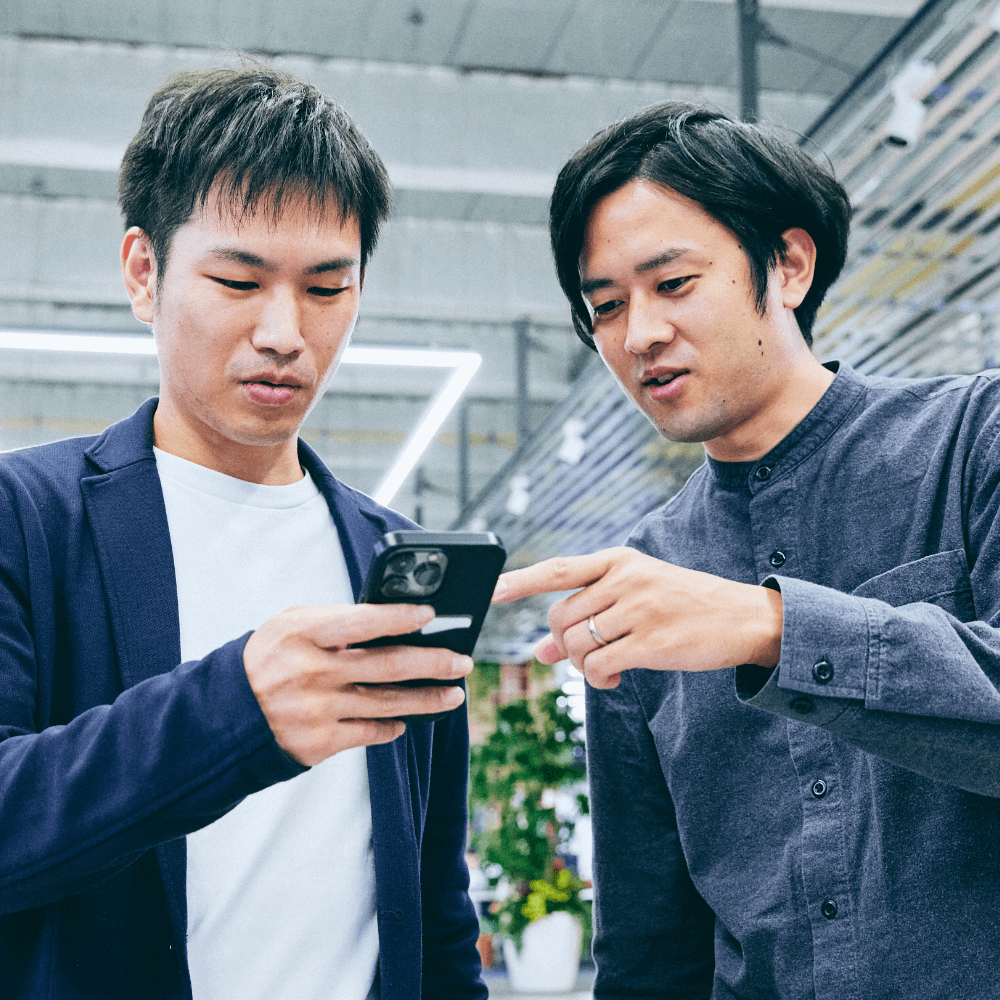
――「Wellness Aile」を労働組合に導入後、どんな反響を得られていますか?
今回、「Wellness Aile」を活用してすごく良かったと思うのは、普段接点の少ない人とも会話をするきっかけとネタ、つまりコミュニケーションの土台が生まれたことです。
会社が大きくなると知らない人も増えますし、自分が関わっているプロジェクト以外の人と接する機会も減りますよね。
でも定期的にチームをシャッフルしながら「Wellness Aile」を楽しむだけで、普段関わっていないプロジェクトの人とも「いつもたくさん動いているけれど何をしているの?」と問いかけるなどをきっかけに会話が自然に生まれるようになったのです。
実際に「毎日ジョギングをしているよ」「週末キャンプに行ったんだよ」「サイクリングを始めたよ」といった会話があり、それをきっかけに労働組合の中で部活のようなコミュニティが生まれるようになりました。
ウェルビーイングとは一瞬の健康や幸せではなく、それが常態化することを指すと考えます。だからこそボトムアップで取り組める「Wellness Aile」は価値があると実感しました。
今はまだ組合内でトライアルをしている状態ですが、「Wellness Aile」は日々小さな成功体験を積み重ねられますし、ウェルビーイングを高めるだけでなくチームビルディングにもつながることがわかってきたので、今後は社内にもっと広めたいと考えています。
Wellness Aileを通して、他社との共創やコミュニケーションを作る

――梓設計のウェルネス領域における、今後の計画について教えてください。
大きく2つあります。
一つは活動データと環境データの相関性を分析し、それをオフィスの省エネや従業員の生産性向上・満足度に活用していくこと。
リアルタイムで、人の動きがわかれば、それに合わせた空調や照明をデザインできるはずですので、スマートホームの仕組みを大きなオフィスでも実現させたいと考えています。
もう一つは、「Wellness Aile」を個別のチームだけでなく大勢が楽しめるようなイベントにつなげて、同じような取り組みをしている企業との交流を深めること。
これからの時代を生きる私たちや次世代にとって、ウェルビーイングの意識を高めて常態化することは必要不可欠です。「Wellness Aile」が他社とのコミュニケーションのトリガーになることを期待しています。
今回我々は、労働組合に「Wellness Aile」を導入したことで、その価値を十分実感することができました。ウェルビーイングを高めるだけでなく、チームビルディングにも寄与してくれるので、全社導入を進めることで、より一人一人に寄りそう会社へと進化したいと考えています。
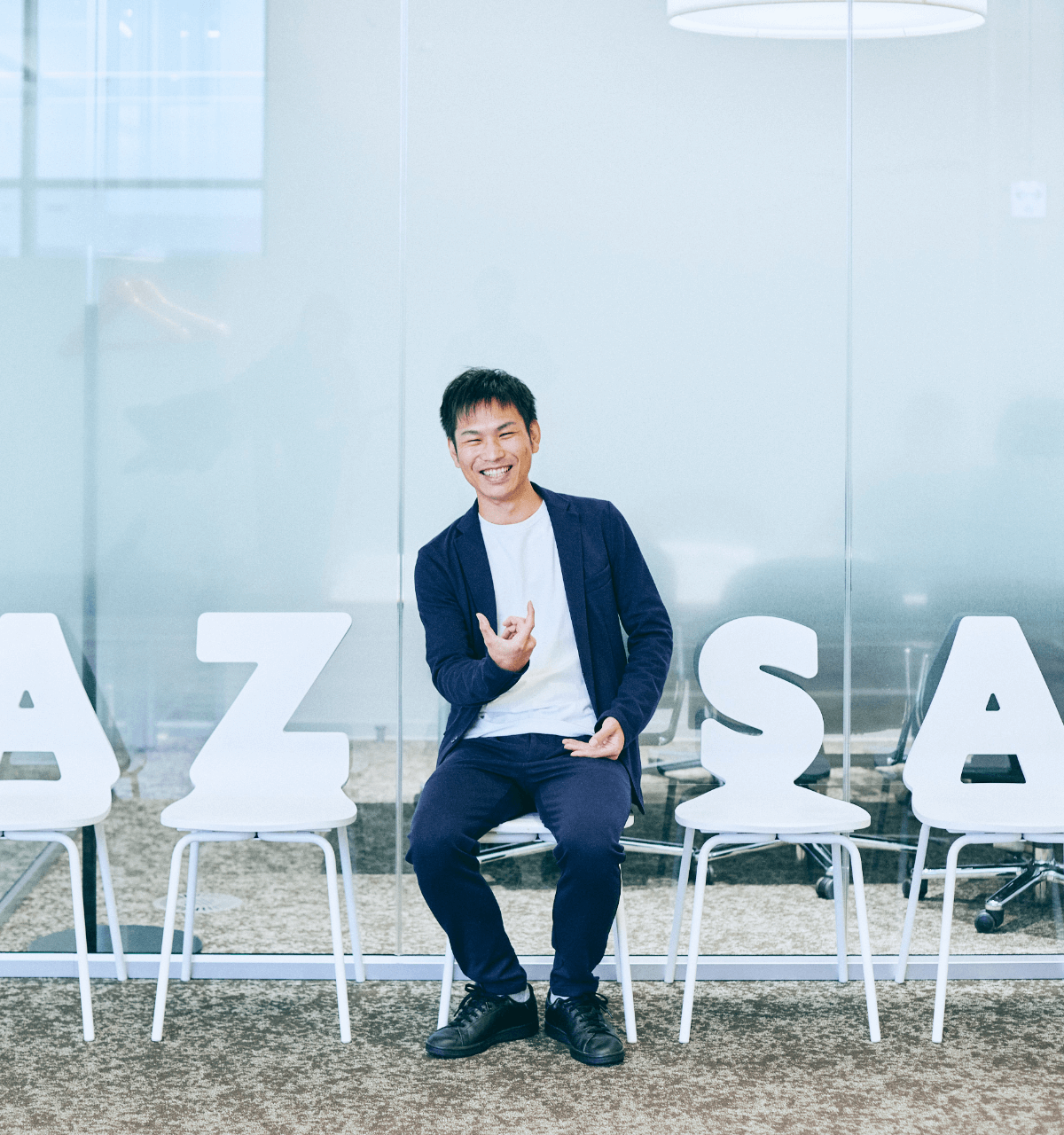

1946年に創設した組織設計事務所。"「建築に温度を」―温かい建築を。誠実に心を込めて―"という信念のもと、社会のニーズに応える建築を、お客様に寄り添って作っていくことを大切にしている。空港施設設計やスポーツ施設設計のシェアで強みを持つほか、庁舎、教育文化施設、医療福祉、物流、斎場、都市再開発など、幅広く公共の施設を設計している。日本国内だけでなく、海外でのプロジェクトも手がける。